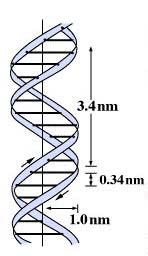「子供は、本当に乾いた砂なのか?」
みなさんは、どうお考えですか?
砂といっても、味気ないとか、小粒であるといった例えではありません。
多くの親たちが持っている、
「子供は、幼いほど乾いた砂が水を吸収するかのように何でも学習することができる」
という考えの中で使われる「砂」です。
つまり、The younger,the better. 。
それを信じて、たくさんの親が、子供に、ピアノ、ヴァイオリン、習字、そろばんは、さすがに少ないでしょうが、語学、特に英語を習わせています。
まるで、自分が、そうしてもらえなかったことへの当てつけのように、幼児にナライゴトをさせているのを見ると、イマドキの子供って大変だなぁとかわいそうになります。
とくに、英語の習得については、親の心の中に、自分がそうしてもらっていたら、何はなくとも、すぐに使えるスキルがあって後の人生が楽だったのに、という後悔めいた気持ちと、子供が、中学になった時に、わざわざ英語で苦労する必要がなくなる、という、二本柱が後押しして、習い事熱はさらにヒートアップするようです。
これがヴァイオリンやピアノの場合だと、たとえ習わせても、よほど才能がないと、趣味にはなっても人生の大きな柱、つまり職業にはならないと考えるためか、熱はそれほど高くなりません。
ここで、最初の疑問に戻ります。
本当に、子供は乾いた砂のように何でも吸収するのか?
わかりやすく、語学に絞って考えてみます。
ここで、臨海期仮説(critical period hypothesis)という考えを引っぱり出しましょう。
語学を身につける、母国語として自由自在に使えるようになるためには学習時期があり、それを過ぎたら不可能になる、という考えです。
多くの親は、これを信じて子供に語学を学ばせています。
たしかに、母国語(第一言語)として、使っているという気持ちすら持たずに使用できる能力を習得するという点では、臨海期仮説は有効です。
ですが、外国語(第二言語)の習得となると、結構イイ大人になっても充分に可能であることは、数多くの例で証明されています。
ここで、第二言語の習得とは、「コミュニケーション」の手段としての言語利用ができる、という意味です。
つまり第二言語の学習において、臨海期仮説は有効ではありません。
思いついたら、いつでも語学学習は可能なのです。
ただ、その時点での環境が、習得度に大きく作用してきます。
海外に住んでいるように、習得希望言語(英語など)が、日常的にしょっちゅう耳に入ってくる場合(外国環境と名付けます)は、「学習しているという意識なし」で、英語を獲得することができます。
この場合は、年齢が若ければ若いほど有利でしょう。
反対に、日本国内に住んで、一日のほとんどを日本語に囲まれて暮らしている場合(国内環境と呼びましょう)は、自然に外国語が耳に入ってくる、ということは考えられません。
この場合は、「学習を意識して」語学習得を目指さなければなりませんが、そうなると動機づけの弱い幼児より、やらねばならないのだ、と自分を納得させられる大人の方が有利だということになります。
子供はすぐに飽きて、集中力、持続力を欠いてしまうからです。
さて、ヤラネバナラヌと決意した大人ですが、やはり外国環境の方が語学習得には有利です。
そのためには、国内にいながら外国環境に近づける努力をしなければなりません。
環境は、まあいろいろできるでしょう。
普段から英語をポータブルプレイヤーで耳に流し込む。
独り言を英語でつぶやく。
英語を学びたいもの同士、英語で会話する
英会話学校に通う。
など。
わたしが外国に住む知人(日本人)たちから聞いたことから判断すると、一番大切なのは、
「それを使わなければ生活(仕事)していけない、という差し迫った必要性(Uegent Need)」
です。
そのため、定期的に近場の英語文化圏を中心に、飛行機の往復切符(できれば30日FIX程度の)をもって、ひとり旅をするのも良いでしょう。2,3日でもかまわないと思います。
そこでは、道をたずねるのも、ホテルにチェックインするのも、ケンカすることにも切実な語学の必要性が生じるからです。
肝心なのは、普段の学習時に、常にそういった差し迫った状況を頭に思い浮かべながら、ただ機械的に、単語とパターン会話の組み合わせで英語を話すのではなく、「ホントウニツタエタイコト」を英語で表す、表現者としての自分を意識しながら学ぶことです。
あれ、随分始めのテーマからずれました。
子供は砂なのか、でしたね。
わたしは、「ヒトは、その思考を、習得する第一言語によって規定される」のではないかと考えています。
言語はすなわち文化であるから。
まあ、規定というと少しきついですから、なんとなく言葉のシバリにあっているということですね。
日本語のように、文の最後に肯定否定がくる言語を使う国民は、優柔不断気味で、雰囲気で話すことが多い、とかね。
しかしながら、以前、ギリシア語が論理的であるということを知って、ギリシア系カナダ人に、
「古代ギリシアで哲学が発達したのは、ギリシア語が、論理の構築に向いた語学であったからではないか」
、と尋ねたところ、
「自分も含め、知り合いのギリシア人は、それほど論理的ではないね」
と一蹴されてしまったことがある。
実際はどうなんだろう。
それでも、上の「言語規定説」が多少なりとも正しければ、「幼児期に複数の言語を同時に学ばせる」のは危険ではないだろうか?
それは、アイデンティティの確立とも関わってくるような気がするから。
3人兄弟で、真ん中の子が、兄貴体質と弟体質の両方を兼ね備えていることがある。
アニキ的に責任感のあるところを見せたかと思うと、突然、弟のように甘えた言動をする。
そういった大きな振幅の人間を、どう扱ったらよいか困ることがあるように、複数の国民性がランダムに出てくる子供がいたら、きっと扱いにくいだろうな。
ともかく結論だ。
「確かに子供は砂である」
どんどんいろいろなモノを吸収するだろう。
だが、砂にも容量がある。
コップ一杯分の砂に、バケツの水は入らない。
ちまたで耳にする幼児教育でも、子供は乾いた砂だ、とばかりに大量の水を流しみ、結局オーバーフローしているような例を見ることがある。
大切なのは、自分の子供の砂が、どのくらいの容量かを見極めながら水をふりかけることだろう。
どうせ、わたしたちの子供なんだから、とんでもなく大きい砂場なわけないじゃないですか。